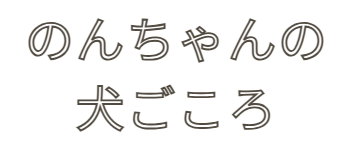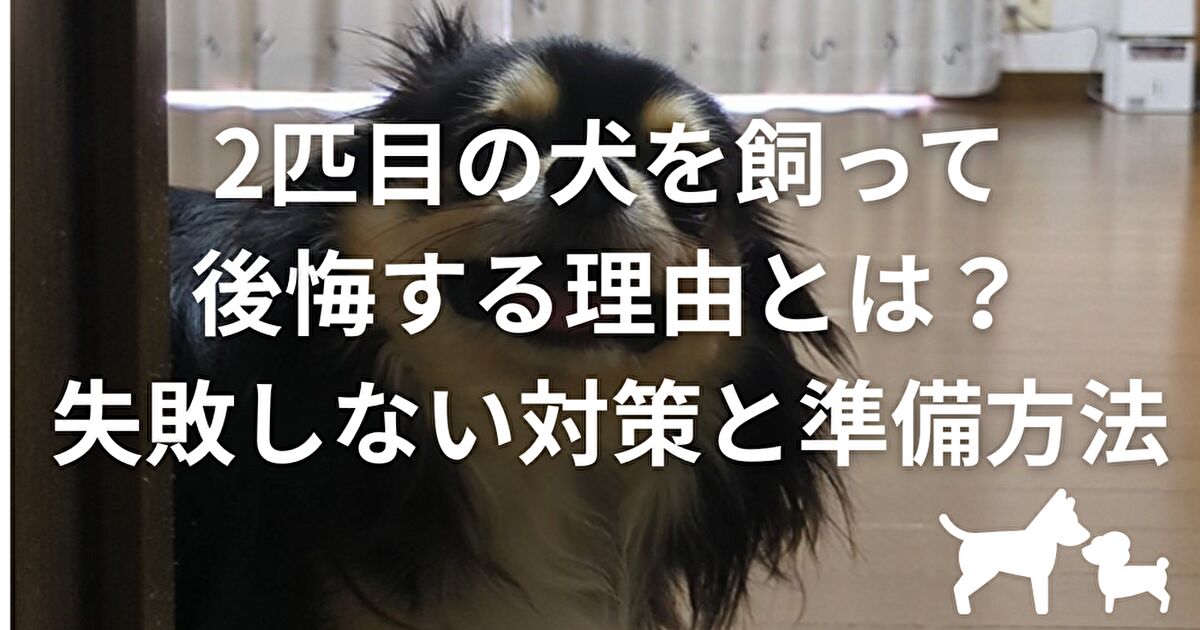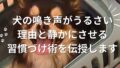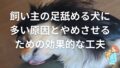ひで(のんちゃんの飼い主)
ひで(のんちゃんの飼い主)
チワワの「のんちゃん」と暮らすひでが運営しています。犬との暮らしの楽しさや悩み、日々のちょっとした発見をブログでシェア中。のんちゃんの可愛い姿や役立つ情報を通じて、読者の皆さんと温かいコミュニティを作っていきたいです。

下の動画は僕とひでのショート動画だよ。ぜひ見てね(^^)/
「犬は一匹より二匹」と聞けば楽しそうに思えますが、現実はそれほど簡単ではありません。先住犬がストレスを抱えたり、犬同士が仲良くなるまでに時間がかかったり、「二匹目が可愛くない」と感じてしまう自分に戸惑ったりする人も少なくありません。
特に2匹目を飼うタイミングや二匹目の初日の過ごし方、 2匹目の会わせ方などは後悔しないために事前に押さえておくべき重要なポイントです。
また、犬同士の仲の悪いサインを見逃すと、関係修復がさらに難しくなることもあります。
本記事では、2匹目の犬を飼って後悔を感じる原因や、犬同士がうまくやっていくための工夫、ケージの配置といった環境づくりまで、実例と共に丁寧に解説していきます。

あなたと愛犬たちが笑顔で過ごせるヒントを見つけてくださいね
この記事を読んでわかること
-
犬を2匹目として迎える際に起こりやすいトラブルや注意点がわかる
-
先住犬にかかるストレスや犬同士の相性問題について理解できる
-
2匹目を迎えるベストなタイミングや適切な会わせ方が学べる
-
多頭飼いに向いていない人の特徴とその対処法が見えてくる
- 2匹目の犬を飼うタイミングを見極めるコツ
- 2匹目の犬 会わせ方の正しいステップ
- 2匹目の犬 初日にやるべき対応とは
- 2匹目の犬 仲良くなるまでに必要な時間
- 犬のケージ 2匹目をどう設置すべきか
2匹目の犬を飼うタイミングを見極めるコツ
 画像出典:キャンバ
画像出典:キャンバ
犬を2匹目として迎える際のタイミングは、単に「飼いたいから」という気持ちだけでは判断できません。適切なタイミングを見極めることで、先住犬との関係性がスムーズになり、飼い主自身の負担も軽減できます。
まず前提として、先住犬が安定した生活を送れているかを確認することが重要です。
しつけが完了しておらず問題行動が頻発するような状態では、新しい犬を迎える余裕がありません。先住犬が安心して生活できていて、飼い主との信頼関係が築けているかどうかを見極めましょう。
次に、飼い主の生活環境にも目を向ける必要があります。
たとえば、仕事が忙しくて散歩やケアの時間が足りていない状態であれば、2匹目を迎えることは控えた方が良いでしょう。多頭飼いは可愛いだけではなく、手間も費用も2倍以上かかることを理解しておくべきです。
また、犬の年齢差もタイミングを決めるポイントになります。先住犬が高齢であれば体力的にも精神的にもストレスが大きくなりますし、逆に若すぎるとまだ性格が安定していないため、トラブルの元になりかねません。
一般的には、先住犬が2歳〜6歳の間に迎えるのが望ましいとされています。
このように考えると、「飼い主の生活リズム」「先住犬の状態」「犬同士の年齢バランス」の3点がそろったときが、犬を2匹目として迎えるベストなタイミングです。
焦らず、無理のない状況を整えてから新たな家族を迎えましょう。
2匹目の犬 会わせ方の正しいステップ
 画像出典:キャンバ
画像出典:キャンバ
犬を2匹目として迎える際、最初の「顔合わせ」がその後の関係性を大きく左右します。つまり、会わせ方を間違えると、犬同士がずっと距離を取る関係になる可能性すらあるのです。
そこで大切なのが、段階を踏んだ会わせ方です。
まずは、中立的な場所で対面させることが最初のポイントです。自宅は先住犬にとってのテリトリーであり、新しい犬をいきなりそこに入れてしまうと、縄張り意識から強い警戒心や攻撃性を示すことがあります。
そのため、最初は公園などの開けたスペースでリードを付けたまま挨拶をさせるのが理想的です。
次に、一緒に短い散歩をすることが有効です。並んで歩くことで、犬同士が「群れ」としての感覚を共有し始めます。このとき、無理に近づけすぎず、あくまで犬のペースに任せて距離を保つことが大切です。
その後、自宅に戻る場合は、新入り犬から先に家に入れず、先住犬の存在を尊重しましょう。
先住犬に自分のテリトリーを確認させた上で、新入り犬をゆっくりと紹介していくことで、トラブルのリスクを減らすことができます。
さらに、最初の数日は完全に一緒にしないという選択もあります。別々の部屋で過ごさせ、匂いを交換する時間を作ることで、徐々に慣れさせることができます。
このように、正しいステップを踏んだ会わせ方は、犬同士の信頼関係を育てる上でとても効果的です。初対面での印象は長く引きずるものですので、慎重に、そして丁寧に進めていきましょう。
2匹目の犬 初日にやるべき対応とは
 画像出典:キャンバ
画像出典:キャンバ
新しい犬を迎えた「初日」は、飼い主にとっても犬にとっても非常に重要な1日です。この日の対応が、その後の生活のスムーズさや犬同士の関係に大きく影響を及ぼします。
まず最初に意識しておきたいのが、刺激を与えすぎないことです。新入り犬にとって、まったく知らない場所での生活が始まるわけですから、不安と緊張でいっぱいです。
このタイミングで多くの人に会わせたり、先住犬と長時間接触させたりすると、ストレスが一気に高まりかねません。
次に行いたいのは、新入り犬の「安全基地」を用意することです。
例えば、ケージやクレートに毛布やお気に入りのおもちゃを入れておくと、犬はそこを安心できる場所として認識します。
これは新入り犬だけでなく、先住犬にとっても自分のスペースが守られている感覚につながるため、双方にとって効果的です。
さらに、食事やトイレの時間をずらす工夫も初日から取り入れたいポイントです。
最初からすべてを同じタイミングにすると、犬同士の競争心が生まれやすくなります。特にごはんは、別々の場所で、目が合わないように与えることでトラブルを防ぐことができます。
また、先住犬をしっかり褒めて安心させることも重要です。新入り犬ばかりに注意を向けてしまうと、先住犬が不安や嫉妬を感じてしまう場合があります。
「あなたのことも大切だよ」というメッセージを行動で示すことで、先住犬の心を安定させましょう。
このように、2匹目の犬の初日は「静かに慣れさせる」「それぞれの居場所を確保する」「先住犬を優先的にケアする」ことが基本です。焦らず、少しずつ関係を築いていく意識が大切です。
2匹目の犬 仲良くなるまでに必要な時間
 画像出典:キャンバ
画像出典:キャンバ
犬同士が本当に仲良くなるまでには、思っている以上に時間がかかることがあります。早ければ数週間で打ち解ける場合もありますが、数ヶ月、あるいは半年以上かかるケースも珍しくありません。
つまり、「すぐに仲良くなるだろう」と期待しすぎると、うまくいかない時に飼い主が不安やストレスを感じてしまうことがあるのです。
犬にはそれぞれ性格があり、環境や過去の経験も大きく影響します。
例えば、もともと他の犬と遊ぶのが好きな社交的な犬であれば、比較的早く距離を縮めることができます。一方、慎重で警戒心が強い性格の犬は、新しい犬との関係に時間がかかります。
特に先住犬がもともと一人で過ごすことに慣れていた場合、2匹目の存在がストレスになることもあるため、無理に接触を促すのは逆効果です。
このような場合は、犬たちのペースに合わせて距離を縮めさせることが大切です。初期段階では一緒に遊ばせようとせず、別々の部屋で過ごさせながら、匂いを交換したり、ケージ越しに様子を見せたりといった段階的な慣らし方が効果的です。
そして、徐々に同じ空間にいさせる時間を伸ばし、喧嘩や威嚇がなければ、少しずつ距離を縮めていきましょう。
また、飼い主がどちらか一方だけをかまいすぎないように配慮することも、関係性を築く上で大切なポイントです。
とくに先住犬は「新しい犬が来て、自分の地位が脅かされている」と感じると、仲良くなることを拒むようになる可能性があります。
こうして考えると、犬同士が本当に心を開いて仲良くなるには、少なくとも1~3ヶ月、慎重なケースでは半年以上の時間を見込む心構えが必要です。焦らず、ゆっくりと信頼を積み上げていくことが何より大切です。
犬のケージ 2匹目をどう設置すべきか
 画像出典:キャンバ
画像出典:キャンバ
2匹目の犬を迎える際、ケージの設置方法は非常に重要なポイントです。
犬は自分のスペースを持つことで安心感を得る動物であり、正しい配置ができていないと、不安やストレスが原因で犬同士の関係に悪影響を及ぼすこともあります。
まず大前提として、2匹それぞれに専用のケージを用意する必要があります。
1つのケージに2匹を一緒に入れることは、一見仲良しのように見えても、ストレスの元になる可能性が高くなります。
犬はそれぞれが安心して休める「自分だけの場所」を必要としており、それが確保されていないと、睡眠不足や神経質な行動が出やすくなります。
次に、ケージを置く場所の距離感にも注意が必要です。最初のうちは、犬同士の距離を適度に保てるよう、ある程度離れた場所に設置しましょう。
例えば、同じ部屋の中でも目が合いにくい位置や、仕切りがある場所が理想です。これにより、お互いに存在を感じつつも、過剰な接触や視線のストレスを避けることができます。
さらに、食事や休憩のタイミングに合わせて、ケージの利用を習慣化させると良いでしょう。
例えば「ごはんの前はケージで待つ」「お昼寝はそれぞれのケージで過ごす」といったルールを設けることで、犬たちが自然とケージを安心できる場所として認識するようになります。
そしてもう一つは、それぞれの犬の性格に合わせて配置を調整する柔軟さも必要です。
例えば臆病な性格の犬であれば、人の気配が感じられる場所にケージを置くことで安心しやすくなりますし、反対に神経質な犬なら、静かな角に設置する方が落ち着けます。
このように、犬2匹目のケージ設置は、「それぞれにケージを」「適切な距離感で」「性格に合わせて配置」という基本を押さえた上で、日常の生活動線とも調和するように整えていくのが理想的です。
設置の工夫ひとつで、犬たちの関係がぐっと良くなることもあります。
2匹目の犬 後悔する人の共通点とは
 画像出典:キャンバ
画像出典:キャンバ
- 2匹目の犬 先住犬のストレスの原因とは
- 犬同士が仲悪いというサインを見逃さない
- 二匹目の犬が可愛くないと感じる理由
- 多頭飼いが向いてない人の特徴
- 犬は一匹より二匹が幸せなのか
- 2匹目の犬 後悔しないために知っておきたいリアルな体験と注意点 まとめ
2匹目の犬 先住犬のストレスの原因とは
 画像出典:キャンバ
画像出典:キャンバ
2匹目の犬を迎えたことで、先住犬にストレスがかかることは珍しくありません。多くの飼い主が「2匹目が来てから、先住犬の様子が変わった」と感じるのは、このストレス反応が関係していることが多いのです。
主な原因のひとつは「生活環境の変化」に対する不安です。先住犬にとって、自分のテリトリーに突然他の犬が入ってくることは、大きな脅威として受け取られることがあります。
特に今まで一人っ子のように手厚く愛情を注がれていた場合、その安心感が揺らぐことで、不安や嫉妬が生まれやすくなります。
もう一つ大きな要因となるのが、「飼い主の注意や愛情の配分」です。
飼い主が2匹目の犬に多くの時間や関心を向けるようになると、先住犬は「自分はもう必要とされていないのでは」と感じることがあります。このような心理状態は、吠える・隠れる・食欲が落ちる・無気力になるなど、さまざまな形で表面化します。
さらに、遊ぶ時間や散歩の順番、寝る位置など、日常のルーティンが変わったことも、先住犬のストレスに拍車をかけます。人間にとって些細に思える変化でも、犬にとっては重要な安心材料であることを忘れてはいけません。
こうしたストレスを和らげるためには、先住犬との時間をこれまで以上に大切にすることが大切です。
たとえば、新入り犬とは別のタイミングで散歩をしたり、先住犬だけと触れ合う時間を確保することで、「自分はまだ大事にされている」と感じさせてあげることができます。
ストレスの兆候を見逃さず、先住犬の気持ちに丁寧に寄り添うことが、多頭飼いを成功させるカギになります。
犬同士が仲悪いというサインを見逃さない
 画像出典:キャンバ
画像出典:キャンバ
犬同士の関係がうまくいっていない場合、飼い主がそのサインを見逃してしまうと、後々大きなトラブルにつながる可能性があります。
仲が悪い兆候は、はっきりしたケンカだけではありません。もっと繊細で見落としがちな行動の中に、そのヒントが隠れていることが多いのです。
まずよく見られるサインのひとつが、「一方の犬が常にもう一方を避けている」状態です。
例えば、目を合わせない、部屋の隅に隠れる、一緒に寝ようとしないといった行動があれば、それは距離を置きたいという意思表示かもしれません。
特に、逃げ場がなくなるような状況が続くと、ストレスが溜まり、やがて攻撃行動に発展することもあります。
また、逆に「一方の犬がしつこく追いかけ回す」「体当たりや吠えが頻繁に起こる」といった行動も要注意です。
これらは遊びに見える場合もありますが、犬の表情や耳・しっぽの動きなどをよく観察すると、緊張や威圧のサインであることが分かります。
他にも、食事中に片方が落ち着かない、オモチャを取り合う場面が頻発する、飼い主の膝の上をめぐって争うような仕草があるといった状況も、関係性がまだ安定していない証拠です。
こうした兆候を見つけたら、無理に一緒にさせるのではなく、物理的に距離をとって休憩させる、飼い主が間に入ってバランスを取るなどの工夫が必要です。
悪化する前に介入することで、犬たちの信頼関係を少しずつ築き直すことができます。
仲良しに見えても、犬たちの本当の気持ちは行動に現れます。日々の様子を細かく観察し、違和感があれば早めに対処することが大切です。
二匹目の犬が可愛くないと感じる理由
 画像出典:キャンバ
画像出典:キャンバ
「2匹目の犬を迎えたのに、なぜか可愛く思えない」このような気持ちを抱えてしまう飼い主は意外に多いものです。
これは愛情が足りないのではなく、状況や心理的な負担によって、一時的にそう感じてしまうケースが多く見られます。
最も大きな要因として挙げられるのは、「先住犬への強い愛着との比較」です。先住犬との絆が深ければ深いほど、新しい犬に同じ感情を抱けず、なんとなく物足りなさを感じてしまうことがあります。
また、先住犬が子犬時代だった頃の記憶と比べて、2匹目の犬の性格や行動が期待と異なっていると、「思っていた子と違う」と感じてしまうのです。
もう一つは、「2匹目が原因で生活が大変になったこと」への無意識のストレスです。
トイレトレーニングのやり直し、夜鳴き、相性の悪さ、散歩や食事の手間などが重なり、「この子が来てから疲れてばかり」と感じるようになると、どうしても感情的な距離ができてしまいます。
さらに、2匹目を迎える際に「もっと感動があると思っていた」という理想と現実のギャップも、愛情の湧きにくさにつながります。
可愛がりたいと思っているのに気持ちがついてこない状況は、飼い主自身にも負担となり、罪悪感を抱いてしまうこともあります。
こうした場合は、無理に「可愛く思おう」とするのではなく、まずは自分の心と向き合うことが大切です。
日々のお世話の中で少しずつ関わりを持ち、スキンシップの時間を設けたり、小さな成長を喜んだりすることで、自然と愛着が芽生えていくことがあります。
時間をかけて築く関係も、初めからの愛情と同じくらい、いやそれ以上に深い絆になることがあります。焦らず、自分自身にも優しく接してあげてください。
多頭飼いが向いてない人の特徴
 画像出典:キャンバ
画像出典:キャンバ
多頭飼いは愛犬との暮らしに豊かさをもたらす一方で、相応の覚悟と努力が必要です。犬が好きだからといって、誰にでも向いているとは限らないのが現実です。
ここでは、多頭飼いに向いていない人の特徴をいくつか挙げてみます。
まず最も大きなポイントは、「時間や心に余裕がない人」です。
1匹だけでも、散歩・しつけ・健康管理などやるべきことはたくさんあります。2匹以上になると、それぞれの犬に合わせたケアが必要になるため、単純に手間が2倍になるだけでなく、トラブルへの対応力も問われます。
たとえば、一方が病気になったとき、もう一方の世話も滞らせずに続けられるかどうか。仕事や家庭の事情で多忙な方には、かなりの負担となる可能性があります。
また、「衝動的に犬を迎えてしまう人」も注意が必要です。
テレビやSNSで可愛い犬の姿を見ると、つい2匹目が欲しくなることはあるかもしれません。しかし、実際の多頭飼いは理想通りにいかないことも多く、犬同士の相性が合わなかったり、先住犬が強いストレスを感じたりすることもあります。
深く考えずに2匹目を迎えると、結果的に飼い主にも犬にも負担となるでしょう。
さらに、「犬の行動や感情に鈍感な人」も多頭飼いには向いていません。犬同士の微妙な空気の変化や、仲が悪くなるサインに気づけなければ、ケンカや問題行動を防ぐことが難しくなります。
多頭飼いでは、犬たちの性格や関係性に合わせた対応が求められるため、観察力や対応力も重要な要素になります。
このように、可愛いからといって安易に多頭飼いに踏み切るのではなく、自分が向いているかどうかを冷静に見極めることが大切です。
犬たちにとっても、ストレスのない環境をつくるのは飼い主の責任です。自信がない場合は、無理に多頭飼いを目指すより、1匹の犬とじっくり向き合う方が幸せな選択になることもあります。

下記の記事も参考にしてね
犬は一匹より二匹が幸せなのか
 画像出典:キャンバ
画像出典:キャンバ
「犬は一匹より二匹の方が幸せ」と言われることがありますが、これは一概には言えません。実際のところ、その答えは「犬の性格」「飼育環境」「飼い主の関わり方」によって大きく変わります。
たしかに、性格の合う犬同士であれば、遊び相手ができたり、留守番中の寂しさが軽減されたりするメリットがあります。
とくに、活発で社交的な犬は、同じように元気なパートナーと一緒にいることで、心身ともに良い刺激を受け、より充実した生活を送れるケースもあります。
散歩や遊びの中で協調性が育まれ、人間には与えられない“犬同士の学び”があるのも事実です。
一方で、すべての犬が多頭飼いに向いているとは限りません。中には、自分だけの空間や飼い主との独占的な関係を好む犬もいます。
そうした犬にとっては、2匹目の存在が大きなストレスとなる場合があり、かえって生活の質が下がってしまうこともあります。
また、犬同士の性格が合わなければ、けんかやトラブルが日常的に発生し、結果として「犬も飼い主も疲れてしまう」という状況になりかねません。
さらに、飼い主の負担も無視できません。2匹目を迎えることで、経済的な支出は確実に増えますし、時間的なゆとりや注意力もより求められます。
「2匹目を迎えたから犬が幸せになる」という発想ではなく、「2匹ともが満足して過ごせるように、自分が責任を持って対応できるかどうか」を軸に判断することが重要です。
つまり、犬が一匹より二匹で幸せかどうかは、状況次第ということです。理想を追い求めるだけでなく、実際の自分の生活スタイルや犬の個性を見つめ直すことが、最終的に犬の幸せにつながる選択になります。
2匹目の犬 後悔しないために知っておきたいリアルな体験と注意点 まとめ
この記事をまとめます。
-
相性が合わず喧嘩が絶えなかった
-
一匹目の世話で手一杯なのに負担が倍増した
-
散歩やごはんのタイミングがずれて手間が増えた
-
出費が倍になり予想以上に家計を圧迫した
-
多頭飼い用の広いスペースが必要だった
-
トイレのしつけがうまくいかずストレスが溜まった
-
一匹目の愛情が分散されてしまったように感じた
-
家族の協力が得られず負担が一人に偏った
-
旅行や外出がさらに難しくなった
-
鳴き声が増えて近所迷惑が心配になった
-
一匹目が精神的に不安定になった
-
犬同士でおもちゃやごはんを取り合ってしまった
-
動物病院代が2倍になり突然の出費が痛手だった
-
しつけの方針がバラバラで混乱を招いた
-
思っていたよりも多頭飼いの覚悟が必要だった