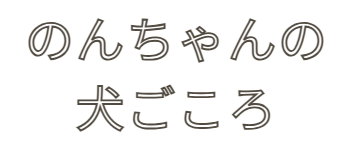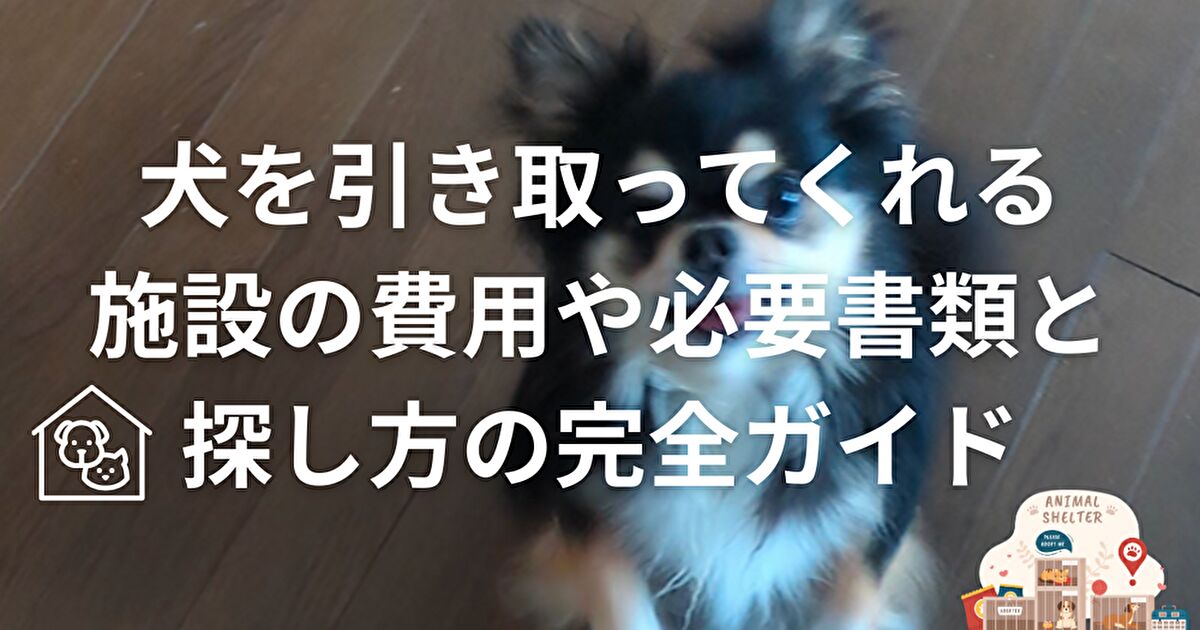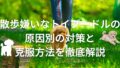犬を引き取ってくれる施設を探している方に向けて、選び方や費用の目安、申し込みから引き渡しまでの手続きの流れを、一つひとつ丁寧に整理します。
犬を引き取ってもらうのに必要な書類や準備物、また犬を飼えなくなった場合にどのような順序で動けばよいのかも、具体例を交えながら解説します。
行政施設と民間施設の特徴や受け入れ条件の違い、終身預かりサービスを利用する際の注意点、さらに地域ごとの施設情報や選び方のポイントまでを網羅。
初めて情報を集める方でも迷わず比較検討でき、後悔のない判断につながるような実用的で信頼性の高い知識をまとめました。

大切な家族だからこそ、最後まで安心できる場所を選びたいですよね。
そんなあなたに必要な情報をそろえましたので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
この記事を読んでわかること
-
行政と民間の特徴と違いがわかる
-
引き取り費用の相場と内訳を理解できる
-
手続きに必要なものと準備の流れを把握できる
-
地域別の相談先と選び方の要点を押さえられる
犬を引き取ってくれる施設の種類と特徴

『犬を引き取ってくれる施設の種類と特徴』は次のとおりです。
ㇾこの章のもくじ
行政施設と民間施設の違い

行政施設(保健所・動物愛護センター)と民間の保護団体や終身飼養施設には、目的・受け入れ条件・アフターケアなどにおいて明確な違いがあります。
行政施設は各自治体による公的な受け皿であり、「やむを得ない事情」の確認が原則として必須です。
例えば、ケガや入院、住居事情など、「譲渡先」を探す努力を既になしているかが審査の基準となるケースがあります。
これは全国的な行政ガイドラインにも準拠した運用です(出典:環境省「犬猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」)。
一方、民間の施設は、営利ではなく「保護」「譲渡」「終生飼養」を目的に運営されることが一般的です。
例えば、老犬や持病のある犬への対応、しつけや社会化支援を含む包括的ケア体制が整っている団体もあります。各団体の医療連携やスタッフの専門性により、犬に合わせた柔軟な受け入れが可能です。

以下に主要な違いを整理した表を改めて掲載します。
| 比較項目 | 行政施設(保健所等) | 民間施設(保護団体等) |
| 主な目的 | 収容・管理・譲渡支援(最終手段として処分対象) | 保護・譲渡・終生飼養(生活環境保持) |
| 受け入れ条件 | やむを得ない事情や譲渡先探しの努力が前提 | 面談・契約・医療方針同意などに基づく柔軟な調整が可能 |
| 費用目安 | 数千円の手数料が多い | 無料〜数万円まで幅があり、医療費や移送費などに応じて変動 |
| 引き渡し後の扱い | 期限内に譲渡先がなければ処分対象になる可能性がある | 里親探しや看取りまで対応する包括的ケアが中心 |
| 情報提供 | 引き渡し後の情報提供は限定的 | 近況報告や面会対応を積極的に行う団体も多い |
このような比較から、単に費用だけでなく、犬の年齢、性格、健康状態、新しい飼い主希望者が望むアフターケアの有無といった要素まで総合して選ぶことが、現実的かつ責任ある選択につながります。
老犬引き取り施設の特徴と選び方

老犬を対象とする施設では、一般の譲渡向け施設とは異なる運営構造や設備が整えられており、選び方には専門的視点が求められます。
まず、老犬施設の特徴として挙げられるのは、定期的な医療ケア体制です。
高齢犬では関節疾患、慢性腎不全、歯科疾患といった慢性的な健康問題を抱える例が多く、それに対応するには獣医師による定期診療や投薬管理が不可欠です。
また、物理的な環境面では、滑りにくい床材や段差の少ない構造、落ち着いた空間設計が生活の質(QOL)向上に直結します。
老犬の終生飼育を前提とする施設では、看取りを含めた覚悟ある受け入れ姿勢が見られ、一部の団体では終身預かり契約という形式で対応している例もあります。
このような施設は、若齢犬向けの譲渡施設とは医療費や維持費の構造も異なり、長期的に安定したケア体制が求められる分、費用や契約内容の透明性が特に重視されます。

選び方のポイントとして重視したい要素は以下の通りだよ。
-
見学の可否:実際に設備と犬の様子を確認できるか
-
医療方針と費用内訳の明確性:診療頻度、投薬体制、費用負担の範囲を文書で把握できるか
-
報告体制:定期的な写真・映像・状況連絡の提供があるか
-
契約内容の透明性:預かり期間、緊急対応、面会可否などを明確に定義された契約書があるか
これらが前もって確認できれば、引き渡し後のギャップやトラブルのリスクを大幅に低減できます。
つまり、高齢犬にとって安心して過ごせる環境を、客観的かつ納得できる条件で見極めることが選び方の鍵になります。
犬を引き取ってもらうのに必要なもの

スムーズな引き取りプロセスを進めるには、犬の情報と飼育状況を整理して準備することが大前提です。
以下に、施設側が必要とする主な項目を表形式でまとめます。
| 項目 | 概要・目的 |
| 身分証明書 | 運転免許証・健康保険証など本人確認のために必須 |
| 犬の基本情報 | 年齢、性別、体重、性格、普段の生活リズムなどを明示する |
| 医療関連の記録 | ワクチン接種履歴、避妊去勢の有無、病歴、通院記録などを準備 |
| 申請書・同意書 | 各施設で所定の様式があるため、記入と署名が必要 |
| 費用負担の見込み | 手数料、医療費負担、移送費などの範囲と支払いタイミングを明確に |
| 連絡手段と報告希望の有無 | 緊急連絡先や、今後の近況報告・面会の希望を明記する |
こうした詳細な情報提供が、施設側の受け入れ判断や里親マッチング、ケア方針策定に大きく寄与します。
特に医療歴や性格は、犬の心理的な適応や譲渡の成功に直結するため、丁寧な整理が引き渡し後の生活の質を左右するといえます。
事前準備が整うほど、より適切かつスムーズな引き取り体制が築けるでしょう。
無料で犬を引き取る場合の条件

犬の引き取りが完全無料で行われるケースは非常に限定的です。
行政施設(動物愛護センターや保健所)の場合は、原則として有料で犬の引き取りを行っています。
やむを得ない事情がある場合でも、無料とは限りません。動物愛護団体に相談することもできますが、費用や条件を確認することが重要です。
民間団体では、引き取りそのものは無料でも、次のような実費負担が発生する場合があります。
実費負担がかかるケース
-
ワクチン接種やフィラリア予防、避妊去勢手術などの医療費
-
犬を施設まで搬送するための移送費や交通費
-
施設内で必要となる特殊ケア(持病治療や特別食など)
契約前に確認すべき重要ポイントは、費用がどの時点で発生し、どの範囲を負担する必要があるかです。
また、「無料」という文言だけで判断するのではなく、契約書や同意書に費用発生条件や返金の有無を明記してもらうことが、後々のトラブル防止に直結します。
したがって、完全無料は例外的であり、現実的には何らかの実費が伴うと考えて準備することが安全です。
犬を飼えなくなった場合はどうするか

飼育継続が困難になった場合、まず最初に検討すべきは犬の環境変化を最小限に抑える方法です。
具体的には、親族や友人、近隣の信頼できる人への譲渡が第一候補となります。この方法は犬のストレス軽減につながり、引き渡し後の環境適応も比較的スムーズです。

もし身近な引き受け先が見つからない場合は、以下の順序で選択肢を広げると効果的ですよ。
選択する順番
-
譲渡会や里親募集サイトの活用
全国各地で開催される譲渡会や、インターネットの里親募集掲示板は、多くの希望者と直接つながる場となります。掲載する際は、写真と性格・健康状態を詳しく記載することが重要です。 -
地域の保護団体への相談
団体によっては、引き取り後に新しい里親を探す活動を行っています。医療費負担や契約条件は団体ごとに異なるため、事前確認が必要です。 -
行政窓口への相談(最終手段)
行政施設は原則として最終的な受け皿であり、譲渡努力の証明を求められる場合があります。
加えて、病気や高齢による特別なケアが必要な犬の場合は、獣医師による往診やオンライン診療サービスを活用し、引き渡しまでの健康維持を図ることも有効です。
必要書類や医療記録を整理し、複数の窓口と同時並行で連絡を取ることが、早期解決への近道になります。

主要な譲渡会・里親募集サイトを目的別にまとめました。
気になる所は公式ページで最新の開催情報・条件を確認してくださいね。
【全国型の里親募集プラットフォーム】
- いつでも里親募集中:全国の保護犬・保護猫の募集とイベント情報を掲載。検索性が高く掲載団体も多いです。
- ペットのおうち:日本最大級のプラットフォームの一つ。応募・掲載ガイドや実績指標も掲載されています。
- OMUSUBI by PETOKOTO:審査を通過した保護団体のみが登録するマッチングサイト。イベント検索も可能です。
-
anifare:医療ケアと連携した譲渡を掲げ、全国で譲渡会も実施。掲載犬の検索ページあり。
【定期的に譲渡会を行う主な団体】
- ピースワンコ・ジャパン:各地域の譲渡会・イベント情報を随時更新。
- ちばわん:関東圏中心に「いぬ親会(譲渡会)」を定期開催。
-
アニマルレフュージ関西(ARK):関西を拠点に里親募集・見学手順を明示。
【自治体ページ(公的情報・講習会・譲渡会の案内)】
-
東京都動物愛護相談センター:譲渡を受ける手順、事前講習、対象団体の譲渡会案内を公開。
応募前にワクチン接種歴や避妊去勢の有無、生活環境、留守時間などを整理し、各サイト・団体の応募規約や譲渡契約をよく確認するとスムーズです。
各団体で審査基準や費用負担、トライアルの有無が異なるため、必ず募集要項を読み込んでください。

あわせて下記の記事も読んでね

犬を引き取ってくれる 施設の利用手順と注意点

『犬を引き取ってくれる 施設の利用手順と注意点』は次のとおりです。
ㇾこの章のもくじ
施設利用前に確認すべき条件

施設に犬を引き渡す前に、必ず確認しておくべき条件は多岐にわたります。
まず、受け入れの可否は犬の年齢、健康状態、攻撃性の有無、ワクチン接種歴、避妊去勢の有無などによって判断されます。
行政施設では、これらに加えて「飼い主が譲渡先を探す努力をしているか」が重要な判断基準となり、努力が不十分と見なされると受付自体が拒否される場合もあります。
民間施設の場合は、面談やヒアリングで以下の点が重視されます。
- 飼育放棄に至った経緯
- 犬の性格や生活習慣
- 医療方針への同意の有無
- 契約条件(面会頻度や報告方法など)
特に、生活パターンや家庭での様子を細かく説明できると、受け入れ後のミスマッチを防ぐ効果が高まります。
例えば、他犬との相性、音や人に対する反応、散歩の頻度などの情報は、施設が最適なケアや新しい飼い主選定を行ううえで不可欠です。
要するに、条件を事前に正確に把握し、求められる情報を揃えた状態で申し込みを行うことが、スムーズで安心な引き渡しへの近道です。
引き取り費用の相場と内訳

犬の引き取り費用は、施設の種別や提供サービスの範囲によって大きく変動します。

おおまかな相場は以下の通りです。
| 引き取り方法 | 料金の目安 | 主な内訳・補足 |
| 行政施設 | 2,000〜6,000円程度 | 手数料が中心で地域差あり |
| 民間保護団体 | 0〜50,000円以上 | 医療費・移送費・一時預かり費が含まれる |
| 終身預かり施設 | 50,000〜300,000円程度 | 環境整備・継続医療・介護対応 |
行政施設では、費用の大半が事務手数料であり、地域によって設定額が異なります。
たとえば、都市部の施設では手数料が比較的高めに設定される傾向があり、地方自治体では低額または免除される場合もあります。
民間保護団体では、犬の健康状態や必要な医療処置によって費用が大きく変動します。特に、病気や怪我の治療が必要な場合は、初期医療費が数万円単位で加算されることがあります。
終身預かり施設は、犬が亡くなるまでの生活全般をサポートするため、費用が高額になりやすいです。
冷暖房完備の室内飼養、24時間スタッフ常駐、定期的な獣医診察など、充実したサービスが料金に反映されます。
費用を単純比較するだけでなく、料金に含まれるサービス内容やケア体制を詳細に確認することが、納得できる選択の鍵となります。
終身預かりサービスのメリットと注意点

終身預かりサービスは、特に高齢犬や持病を抱える犬の飼い主にとって重要な選択肢です。
最大のメリットは、殺処分のリスクを回避しつつ、犬が安心して余生を送れる環境を提供できる点です。
こうした施設では、以下のような設備やサービスが整っていることが多いです。
- 冷暖房完備の広い室内飼養スペース
- 滑りにくい床材やバリアフリー設計
- 定期健康診断と常時獣医師との連携
-
個別の食事・投薬スケジュール管理
これらにより、犬は安定した生活リズムを保ち、身体的・精神的な負担を軽減できます。
一方で注意すべきは費用面と契約条件です。終身預かりは数十万円から場合によっては百万円以上かかることがあり、長期的な支出計画が必要です。
また、契約内容には以下の項目が明記されているか確認することが大切です。
-
面会可能な頻度や条件
-
定期報告の方法(写真・動画・書面など)
-
医療判断の最終権限の所在
-
緊急時の対応手順と費用負担
契約は必ず書面で交わし、口頭説明だけで判断しないことが、後のトラブル回避に直結します。
施設見学を行い、犬が実際に過ごす環境を自分の目で確かめてから決断することが推奨されます。
地域別の主な引き取り施設概要

犬の引き取り条件や対応は、地域ごとの行政・民間の連携状況や地理的条件によって異なります。

以下は全国を大まかに区分した傾向の概要です。
| 地域 | 公的窓口の基本方針 | 民間の傾向 | メモ |
| 北海道 | 広域のため事前相談必須 | 個別対応が多い | 移送実費の確認が必要 |
| 東北 | 譲渡努力を重視 | 終身飼養の団体あり | 冬季の移動手段確認が必須 |
| 関東 | 窓口と団体が充実 | 老犬・医療対応施設が多い | 事前講習や面談を伴う |
| 東海 | 譲渡努力が前提 | 問題行動リハビリ対応例あり | 都市部は制度連携が進む |
| 北陸 | 県単位窓口が中心 | 小規模ボランティアが点在 | 審査や講習の確認が必要 |
| 近畿 | 活発な受け入れ体制 | 看取り対応団体が複数 | 家庭訪問や講習が一般的 |
| 中国 | 限定的受け入れ | 老犬・病犬受け皿あり | 島しょ部は持ち込み前提 |
| 四国 | 条件は厳格 | 小規模団体が密着型運営 | 準備の丁寧さが鍵 |
| 九州 | 譲渡イベント活発 | 終身預かりの選択肢あり | 掲示板型の支援も有効 |
| 沖縄 | 事情説明を重視 | 本州連携の団体あり | 収容枠制限で早期相談が必須 |
信頼できる施設を選ぶためのチェックポイント

犬を安心して託すには、施設の信頼性を多角的に評価することが欠かせません。
以下の項目は、事前確認すべき代表的なポイントです。
-
見学の可否と対応態度
見学を拒否する施設は、運営体制や環境面に問題がある可能性があります。事前予約制であっても、犬舎や飼育スペース、医療設備などを案内してくれるかを確認しましょう。 -
スタッフの常駐体制
24時間常駐か、夜間は無人かによって安全性が大きく異なります。常勤スタッフ数や資格(愛玩動物飼養管理士、獣医師など)も判断材料となります。 -
獣医との連携状況
施設内に獣医がいる場合や、近隣動物病院との提携があるかを確認することで、急病時の対応力を把握できます。 -
緊急時の判断基準と手順
事故や急病が発生した場合、どの段階で飼い主に連絡し、どこまで施設側が判断して処置を行うのかを明確にしておく必要があります。 -
費用内訳と契約条件の透明性
費用の項目(医療費、食費、施設維持費など)が細かく記載されているか、追加料金が発生する条件が明確かを契約書で確認しましょう。 -
報告・面会の運用方法
定期的な写真や動画による近況報告の有無、面会可能な頻度と手順は、犬の安心と飼い主の信頼感に直結します。 -
清掃・消毒の頻度と環境管理
施設内のにおいや清潔感、消毒の頻度などは、犬の健康管理の質を映す重要な指標です。
口コミや評判は参考になりますが、必ず現地での確認を行い、言葉と実際の運営状況に矛盾がないかを確かめることが、最終的な信頼性判断に有効です。
犬を引き取ってくれる 施設の活用方法 まとめ
ここまで解説してきた内容を踏まえ、犬を引き取ってくれる施設を選び、活用する際の重要ポイントを整理します。
-
行政施設と民間施設の違いを把握し目的に合った選択を行う
-
老犬対応施設は医療方針や看取り体制の確認が不可欠
-
犬を引き取ってもらうのに必要なものを事前に揃えておく
-
無料引き取り条件は詳細を契約書で確認する
-
飼えなくなった場合は知人や地域ネットワークから当たる
-
行政・民間とも受け入れ条件を事前確認することが重要
-
引き取り費用は金額だけでなくサービス内容も比較する
-
終身預かりは費用と契約条件の精査が欠かせない
-
地域ごとの施設特性と輸送条件を理解して選択する
-
見学やスタッフ対応から施設の信頼度を判断する
-
獣医との連携体制が整った施設を優先する
-
緊急時の対応手順が明確な施設を選ぶ
-
費用内訳と追加条件の透明性を契約書で確認する
-
定期報告や面会の条件を事前に把握しておく
-
清潔で安全な飼育環境を維持する施設を選択する
この記事を書いた人

チワワの「のんちゃん」と暮らすひでが運営しています。
犬との暮らしの楽しさや悩み、日々のちょっとした発見をブログでシェア中。
のんちゃんの可愛い姿や役立つ情報を通じて、読者の皆さんと温かいコミュニティを作っていきたいです。

この動画は僕と飼い主のひでのショート動画だよ。
ぜひ見てね(^^)/